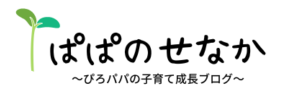七五三は通過儀礼の一つですが、子どもとその家族にとっては一生に一度のイベントです。
どうせお祝いするなら、家族みんなが笑顔で素敵な思い出にしたいですよね。
それには、どんな準備が必要でしょう。
七五三を成功させるための秘訣を教えます。子育て中のママとパパ、参考にしてください。
七五三とは、どんなお祝い?

子どもの成長を、家族みんなでお祝いする日本伝統のイベントです。
女の子は3歳と7歳、男の子は3歳と5歳の年に行います。着物をきて神社にお参りしたり、家族で記念写真を撮ったり、さらに食事会も行うなど、家族みんなで無事に成長したことをお祝いします。

七五三は数え年?満年齢?どっち?
お子さんの成長は早く、2歳と3歳では身長や見た目など1年で大きく変わることもあります。
まだ赤ちゃんの頃のあどけなさが残るうちに写真に残したいなら、数え年でお祝いするのが良いでしょう。
しかし、2歳では着物を着てしっかり歩くことがおぼつかないことも多いので、しっかり歩いてくれず、すぐに疲れてしまいます。
心配な場合には、3歳になってからお祝いをすると良いでしょう。
あとは、兄弟姉妹がいる場合はどちらかに合わせて一緒にお祝いするのもいいでしょう。
現代の七五三はお子さんの年齢に合わせて時期を選ぶことが多くなっています。
混雑期を避けてのお参りもあり!
11月15日の前後になると神社も混雑するので、ゆっくり参拝し、境内で写真を撮ったりするなら、時期をずらすのもおすすめです。
ベストショットがとれそうな場所にはどうしても人が集中するので、順番を待ったり、シャッターを急いで切らざるを得ない場合もあります。
でも、空いている時期に行けば、しっかり構図も考えて撮影することができるでしょう。
六曜と時間帯、曜日でも混雑は変わる
一般的に、
友引も大安に続いて良い日
先勝は午前中が良く、午後は良くない
赤口、先負、仏滅の日には神社への参拝はあまりよくない
と、されています。
当然、神社の混雑具合としては、土日祝日で大安の日だともっとも混み合います。
周りの人を気にせずゆっくりお参りをしたいと考えていて、平日の参拝ができるなら、そちらをおすすめします。
混雑する大安の日でも、特に混み合う午前中を避けて参拝するのも良いですね。
早めの準備こそが成功の秘訣!
七五三には、晴れ着を決めたり記念写真の撮影をしたり、神社にお参りに行ったり、食事会をするなど、準備することが沢山あります。
慌てて準備をして当日に困ることがないように、早めに準備をすることが大切です。
最近では、日焼けをしてしまう前の5月頃から、七五三の撮影をする方が大変多くなっています。
混雑を避けるため、事前に記念写真だけスタジオで撮影して、当日はお参りだけする方も多いですよ。
お子さんの体調や機嫌も考慮しましょう
七五三を成功させるためには、主役であるお子さんの体調や機嫌についてもあらかじめ対策をしておきましょう。
七五三のシーズンである11月は、寒い時期で風邪をひきやすくなっています。
急に熱を出すことが多いお子さんの場合は、予約なしでもお参りできる神社を探すなどの準備をしておきましょう。
多くの参拝客でいっぱいになる神社の場合、お子さんの機嫌が悪くなってしまうことも考えられます。
早めの時間にお参りするか、時期をずらしてピークを避けることも考えておくと良いでしょう。
身内に不幸があった年はどうする?
身内に不幸のあった年のお参りは、基本的には忌中を避ければ良いとされています。
忌中の期間は故人との関係によって異なります。親から見て、配偶者、父母に不幸があった場合は50日間が忌中になります。その期間を避ければ、神社への参拝、神棚へのお参りができます。
もっとも神社によっては喪中(1年間)の参拝を避けるところもありますし、参拝の方法も、鳥居をくぐらないようにする、拝殿の正面で参らないようにするなどのルールがあるところがありますので、参拝予定の神社に相談してみると良いでしょう。
まとめ;家庭の都合に合わせてお祝いをしよう!
七五三のお祝いをするお子さんがいるけれど、ママが二人目の赤ちゃんを妊娠して体調が思わしくない、などというケースも少なくはありません。
家庭によって事情はさまざま、そういった場合は無理に11月15日にお参りに行くことはありません。
必ず11月15日に行かなければいけないと考えるのではなく、前後1、2ヶ月にあたる9~12月初旬ぐらいで、お子さんやご家族の良いタイミングにお参りをしたり、写真を撮るようにしましょう。