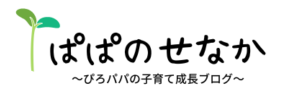そんな疑問にお答えします。
「人生100年時代」と言われる今、保険業界でも「死亡保険」から「生きる保険」へと変化しています。
医療技術の進歩によって、仮に重い病気にかかったとしても生き残れる可能性が高くなりました。
しかし、それは健康な状態で長生きするのではなく、後遺症が残ったり身体機能が低下して要介護状態(生活で人の援助が必要な状態)になってからも長く生きていくことを意味しています。
ある調査報告によると、介護に月額10万円以上かかる世帯が3割、介護を行った年数が4年11か月(平均)といったデータもあります。
そんな時代の流れに合わせて必要とされる保険も変わってきました。ここでは「人生100年時代」に備えるべき保険と、介護保険制度について解説します。
人生100年時代に備えるべき保険はこれだ!

人生100年時代を向かえ、今、もっとも必要で備えるべき保険はこれ!
①就業不能保険
②民間の介護保険
就業不能保険は、現役世代の働けないリスクに備える最近ブレイクした保険です。
そして、次にヒットする保険が「民間の介護保険」です。100歳まで生きる人が増える中、老後世代の介護リスクに備えた保険です。
そんな中すでに急成長している保険が「認知症保険」で、名前の通り保証する範囲を認知症に絞っています。
実際、理学療法士として病院で勤務していると、患者さんの退院の方向性を決めるときに経済面がネックとなり施設への入所や介護サービスの利用を渋るケースが多々見受けられます。
これは他人ごとではありません。子どもの成長とともにご両親も年を重ね、病気をしやすくなり介護が必要な状態になります。その時に慌てないように準備をしておく必要がありますね。
公的介護保険制度とは
「公的介護保険制度」とは、要支援または要介護の認定基準にしたがって等級が決まり、その認定の度合いによってそれぞれの限度額に合わせたサービスを受けられる制度。
認定の度合いが重いほど、限度額が上がり多くの介護サービスを受けることが出来ますが、同時に自己負担費用の総額もその分上がります。
公的介護保険制度には、介護の状態を悪化させないことで全体の費用を抑える「介護予防」の役割も担っており、軽度の介護状態のときにリハビリや運動などのデイサービスを受けることで、寝たきりを避ける効果があります。
<介護保険の区分と限度額>
| 区分 | からだの状態 | 一か月あたりの支給限度額 |
| 要支援1 | 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態 | 5万30円 |
| 要支援2 | 生活の一部について部分的に介護を必要とするが改善が見込まれる状態 | 10万4730円 |
| 要介護1 | 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態 | 16万6920円 |
| 要介護2 | 軽度の介護を必要とする状態 | 19万6160円 |
| 要介護3 | 中等度の介護を必要とする状態 | 26万9310円 |
| 要介護4 | 重度の介護を必要とする状態 | 30万8060円 |
| 要介護5 | 最重度の介護を必要とする状態 | 36万650円 |
介護認定を受ける人は年々増加
介護認定を受ける人が年々増え続けており問題となっています。
2000年度に始まった公的介護保険制度ですが、現在の認定者数は2000年度と比べると約2.4倍、75歳以上は約531万人で全体の約86%を占めています。特に要介護1と認定される人の数が多いです。
住宅改修や介護用ベッドの購入などに使う一時費用、月々にかかる諸費用を合わせると、介護費用の総額は(介護を行った期間の平均値で)500万円以上かかります。
公的介護保険の自己負担額は増える一方
今年8月の公的介護保険制度の改正で、一部の人の負担額は増大❢
もともと1割負担が基本だったはずなのに、3年前の改正時には一定以上の所得がある人に対しては2割負担に、そして今回の改正で特に所得の高い層については通常の医療費と同じ3割負担・・・・・・(+_+)
この流れはおそらく止まらないと思われ、今後も介護サービスの費用負担はますます増えていくことでしょう。これを補完するために生まれた保険が「民間の介護保険」なのです。
家族を守るパパとして、もしもに事態に備える大事な保険をしっかり選びたいですね。